Act1-4
Act 2
2004年8月9日
【巻頭言】
新しい劇空間を求めて
市川 明
「希望とは道のようなものだ。人の歩くところに道はできる」。魯迅の短編『故郷』の言葉は、内藤裕敬のウルトラマーケットの実験に通じる。関西の相次ぐ劇場閉鎖の中で、内藤は自ら道を切り開き、新しい劇空間を生み出したのだから。大阪城ホールの西倉庫を改造したウルトラマーケットで『日本三文オペラ』が上演された。新しい劇場への興味からか、小劇場を結集させた伝説の上演の再再演からか、会場は熱気に包まれ、満員だった。「新しい皮袋に新しい酒」を盛り込めたかどうかは別にして、すばらしい門出に大きな拍手を送りたい。
ニューヨークでは中村勘九郎率いる平成中村座が、都会のど真ん中に江戸時代の歌舞伎座を再現させ、『夏祭浪花鑑』を上演した。新しくて古い日本の建物の突然の出現にニューヨークっ子たちも驚いたことだろう。「歌舞伎は江戸時代には現代演劇だった」という勘九郎の持論が今回どのような形で現れるのか、扇町公園での上演を思い出しながら興味深くニュースを見た。最終場面では光のホリゾントから捕り手たちに混じって銃を構えたNY警察の警官が走りこんできて、大いに沸いたらしい。「伝統と現代が両立する」この上演は、熱狂と高い評価を受けた。
ドイツの演劇が本当に面白かった80年代の初め、ドイツ中部のボーフムには「BO(ボー)工場」という演劇運動があった。巨大な廃工場が、劇空間に生まれ変わった。ブレヒトの「屠畜場の聖ヨハナ」を見に行ったが、見上げるほどの高い渡しに女性が一列に座ってシカゴの株式市況をタイプライターに打ち込んでいる。(今で言えばパソコン入力だろう。)演じられる場所は場面ごとに変わっていく。観客はゴルフのギャラリーのように、工場の端から端まで移動していくのだ。牛も工場内を歩いて、上演に参加している。
犬島の銅精錬場跡を使った、維新派の『カンカラ』公演は衝撃的なイベントだった。過疎化した島の村おこしに演劇は大いに貢献したことだろう。その維新派が今年の秋には、大阪の南港に戻ってくる。京都の明倫小学校跡は京都芸術センターに生まれ変わり、大阪の元精華小学校の体育館は、この秋「精華小劇場」として再生すると聞く。演劇は祭りのようなもの。人の集まるところにシアター(劇場=演劇)はでき、シアター(劇場=演劇)のあるところに人は集まる。
(AICT〈国際演劇評論家協会〉日本センター、関西支部長)

大阪城ホール西倉庫「ウルトラマーケット」。南河内万歳一座のウェブサイトから

2004年「日本三文オペラ 疾風馬鹿力篇」©面高真琴南河内万歳一座のウェブサイトから

2002年7月「カンカラ」©福永幸治 維新派のウェブサイトから
目次
【劇評】すぐれた演出が欠いた求心力――RSC『オセロー』 太田耕人
【時評・発言】
諫早発大阪行(博多乗換)
星野明彦
演劇の教育と俳優の養成 (2) 菊川徳之助
【書評】
杉山太郎著『中国の芝居の見方』に寄せて 藤野真子
すぐれた演出が欠いた求心力――RSC『オセロー』
太田耕人
英国のロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)が、ロンドンのバービカン・センターを去ってずいぶん時が経った。ストラットフォードでも小劇場ジ・アザー・プレイスが一昨年、稽古場に転用された。本拠となる劇場は、シェイクスピア記念劇場とスワン劇場のみになってしまった。
その都度ウエストエンドで劇場を借り、ロンドン公演を打ってはいるが、内容面でも動員面でも退潮の印象はぬぐえない。今年、芸術監督に就任したマイケル・ボイドはロンドンに新しい本拠を構想しているらしい。しかし、まずは評価される舞台を創ることが先決である。
そんなRSCにあって、独り気を吐くグレゴリー・ドーランが、2月にスワン劇場で『オセロー』を現代風の衣装で上演した。この作品が4月の東京公演のあと、5月8・9日にびわ湖ホールにも掛かった。1970年以来、RSCの来日はこれで17回、20作目になる。
演出の最大の工夫は、英国植民地時代、1950年代のキプロスに舞台を設定したことだ。トタン板でできた、格納庫を思わす空間。イアーゴーの罠にかかったオセローを閉じ込めるような、高い金網のフェンス。その向こうを、イスラム風の黒いヴェールの女たちが通る。イスラム世界にキリスト教国がつくった占領地のイメージは、むろん現在の中東につながる。ちなみに当時のキプロスは反英テロが頻発。1960年に独立するものの、その後は民族対立が激化することになる。
キプロスに駐屯する兵士らは酔うと、ジョッキを頭にのせて大声で唄い、みんなでキャシオーを放り投げてシーツで受けとめる。このように男同士が結束した集団は女性蔑視(ミソジニー)に傾き、女を娼婦扱いしがちだ。妻エミリアがオセローやキャシオーと寝たとイアーゴーが疑る箇所や、キャシオーのビアンカへの冷ややかな態度が際立つ、上演になった。リサ・ディロンが扮す英国の良家のお嬢さん然としたデズデモーナも、娼婦としての女性像を裏返した偶像にすぎない。オセローの嫉妬に官能的なものが漂わないのは、彼女が生身の女ではないからだ。
この平板な女性観に異議を申し立てるように、アマンダ・ハリスが異色のエミリアを造形した。トレンチコート姿で登場したエミリアは、煙草をふかし、ウイスキーをあおる。イアーゴーとの生活を乗りこえてきた、年増のしたたかさを覗かせる。ワーキング・クラス訛りのせりふに、世故にたけた貫禄があった。
劇の冒頭ちかく、強烈な差別意識をみせるブラバンショーと対峙して、カ・ヌクーベ演じるオセローは威厳をみせる。後半、嫉妬に悶えて、ズールー族の雨乞いの踊りをおどり、アフリカ性を露わにするのも悪くない。もはやヴェニス的な行動規範をオセローは守れなくなるのだ。しかし丁寧にせりふを語ろうとするあまり、激情が十分に高まらない。語尾の子音をつねに際だたせる癖がある反面、ときおりせりふの細部をのみこむ。そのために、韻文らしい澄み切った荘重さが出ない。
イアーゴー役は、速度にあふれた知的な演技でリチャード三世を演じ、一世を風靡したアントニー・シャー。だれもが、さっそうとしたスマートな悪党ぶりを期待した。だが意外なことに、シャーが扮したイアーゴーは、ずんぐりとした中年の下士官。カーキ色の軍服、鼻下にはヒゲ、腰のうしろで手を組み、胸を張った姿勢は、どこかチャップリンの『独裁者』のヒトラーのようだ。他の兵士とちがう円筒型の制帽は、旧フランス植民地で差別政策の手先となった警官をほのめかす。口ごもることで、偽りの実直さを滲ませるせりふ術は、たしかに達者。だが屈折はしていても、シャーのイアーゴーには狂気じみたところがない。狂気の奥にあるはずの、壊れそうな弱さがみえない。
キプロスをポストコロニアルな視点であつかい、中東をほのめかした演出の切り口はするどい。南アフリカ共和国出身のシャーとカ・ヌクーベを配した上で、植民地出身のオセロー、キプロス生まれのビアンカへの差別を前景化した。だがそのモチーフがつよく出すぎた。その分、愛の悲劇としての劇の求心力が弱まってしまった。めずらしく副筋のないこのシェイクスピア劇は、黒人将軍の激情が差別の問題と表裏一体となり、究極的には神話的規模にまで高まることがのぞましい。
(おおた・こうじん/京都教育大学教授)
Michael Boyd 1955-2023 1986年にアソシエイト・ディレクターとしてRSCに参加、2012年まで芸術監督を務める。2006年4月からシェイクスピア・フェスティバルを開催、2010年新しいロイヤル・シェイクスピア・シアターを開場。
Gregory Doran 1958- 1987年俳優としてロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)に入団、のち演出に転じる。マイケル・ボイドの後任として、RSCの芸術監督に就く。
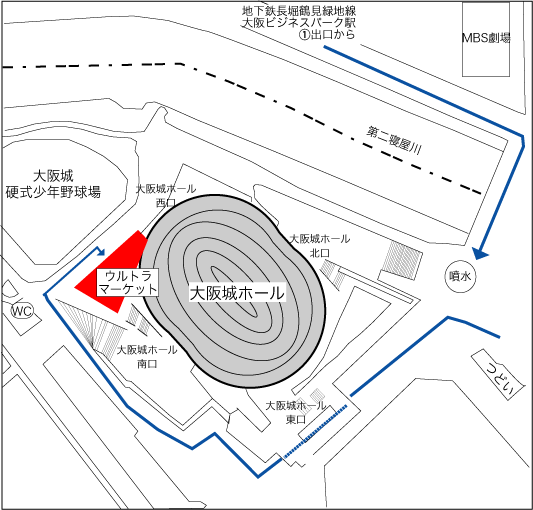
関西の劇団の祝祭劇「日本三文オペラ――疾風馬鹿力篇」
宮辻政夫
劇場閉鎖が相次ぐ関西で、新たにオープンした――というより、内藤裕敬をはじめとする「南河内万歳一座+天下の台所改善隊」の努力によりオープンに漕ぎ着けた――ウルトラマーケットの柿落とし公演である(5月17日~23日)。
開高健原作、内藤台本・演出。終戦間もない頃、大阪城付近にあった旧大阪陸軍砲兵工廠跡地へ、大砲・戦車などの残骸や鉄材を盗みに集まってきた集団の話である。砲兵工廠は終戦直前に空襲を受けて壊滅、焼け野原になり、そこには大砲、戦車などの鉄材が埋まったままだった。時しも朝鮮戦争のため鉄の値段が高騰。このため鉄材に群がる人間達が現れたのだ。この集団は、在日も含む社会の底辺層であり、神出鬼没、アパッチと呼ばれた。上演場所のウルトラマーケットは大阪城ホール内西倉庫のことであり、アパッチが生息していた付近にあり、まさにご当地公演である。
幻の作家を探している青年フクスケ(山下平祐)が登場。アパッチの仲間に引き入れられ話が展開してゆく。リーダー格のキム(木村基秀)、その女房(ののあざみ)を中心にラバ(宮腰健司)、メッカチ(瀬口昌生)、ゴン(信平エステベス)、トクヤマ組長(隈本晃俊)、オオカワ組長(荒谷清水)、マツザワ組長(三浦隆志)らが登場する。
コの字形に組まれたバラックのセットに、出るわ出るわ50人~60人。レスリング的乱闘あり、叫び声あり、大笑あり。乱雑、騒擾、狼藉、猥雑。舞台は、生きる欲望を剥き出しにした、ハダカの、ナマのエネルギーの坩堝と化す。これこそ当時のアパッチの持っていたエネルギーかと思わせる。また「アパッチ」なるものを舞台に描き出す際に必須のイメージだとも感じさせる。つまり、実際そうだったかどうかは別として、アパッチを描いて納得させるのである。
86年、梅田のコンテナヤード跡地での初演もまた、このようなエネルギーに満ちていた。初演時のラスト、背景がトラックと共に一気に芝居小屋の外の闇の奥へと去ってゆき、そこに乗っていた紅萬子ら出演者たちは「わあー」と叫んで手をいっぱい観客席に伸ばして消えていった。唐十郎ばりではあるが、あの場面のエネルギー。それは、関西の小劇場演劇が力を付けて来ていた時期に重なっていた。
91年、京橋の特設テントで古田新太がキムを演じた再演時もエネルギーが溢れていた。この時は、関西の小劇場演劇が、まさに近付くピークに向かって上り坂を駆け上がっていた。
では今回は――。劇場があちこちでなくなってしまった。だが劇場を開拓して手に入れた、その再出発のエネルギーに重なっている。ただ今回は舞台に横溢するエネルギーの質が、初演と比べて変わっているように思われた。初演時よりも可愛い、安全なエネルギー、とでも言うか。俳優達は達者だが反面可愛く、毒が少ない(これは非難の意味ではなく、時代の変化を言っている)。
しかし舞台に溢れるエネルギーとともに、初演から一貫しているもの。この芝居を支える精神は変わらない。それは、祝祭劇の精神。終戦直後、社会の底辺でバイタリティに溢れ、したたかに生きてゆく猥雑な人間達。それらを堂々と力強く、一種憧れさえ交えて描く。直接的にはアパッチへの、間接的にはアパッチに重なる猥雑な人間達への、讃歌。そこに表現されるエネルギーの質が時代によって変わろうとも、その精神は同じだ。見ていてわくわくさせられる。観客もまた騒擾に参加し、お祭りに加わっている気分になる。これが3演とも南河内万歳一座の単独公演ではなく、関西の多くの劇団が協力して出来た舞台であることは、偶然とは思われない。祝祭劇だからこそ関西の劇団を集める力があるのだろう。大阪の、関西の劇団の、手に入れた劇場の?落としの、祝祭劇であった。
さて芝居のストーリーに触れると――。守衛の倉庫にある銀を盗みもうという計画がもたらされる。リーダー格のキムが乗り気にならない、などの展開があった後、結局、決行されるのだが、これは当局の罠で、機動隊の待ち伏せに遭って、アパッチは大打撃を蒙ってしまう。裏切り者がいたのだ。ラストシーン、アパッチの巣窟から去ってゆこうとするフクスケが鞄を開けると、中から強い光が射してくる。それは倉庫にあった銀かもしれないし、あるいは探していた幻の作家(の精神)に行き当たったのかもしれない――。ののあざみがしっかりした演技であった。
幻の作家探しという枠組は、再演時から出て来た。これはこれでいい展開である。しかし初演時の脚本もまた、なかなか優れていたと思う。足の不自由な少女(岡田朝子が演じた)、裏切り者の苦悩など、ドラマチックな内容であった。いつか初演版もまた見たい。
(みやつじ・まさお/毎日新聞編集委員)
郭宝崑 Kuo Pao K'un 1939-2002 シンガポールの劇作家、演出家。北京語と英語で執筆した。1976年から4年半国内治安法にふれるとして拘留された。シンガポール演劇のパイオニアとして内外で認められ、シンガポールの演劇への貢献により1990年にカルチュラルメダリオンを受賞した。

郭宝崑戯曲集『花降る日へ』2000年、れんが書房新社
反戦の意志と複雑な日本への感情-トリプルエム『霊戯』
瀬戸宏
トリプルエムという劇団が郭宝昆『霊戯』を、天王寺の小劇場ロクソドンタブラックで上演することを知ったのは、インターネットで関西地区の上演情報を調べている時で、全くの偶然であった。トリプルエム誕生公演とのことだったが、即座に観に行くことを決めた。2002年に63才で亡くなったシンガポールの劇作家郭宝昆に私は数回会ったことがあり、戯曲集も送ってもらっている。『霊戯』自体、1998年に香港で開催された第2回華文戯劇節で郭宝昆自身の演出による舞台を観ている。郭宝昆が優れた劇作家であることは、日本でも黒テント上演の『KAN-GAN』などで少しずつ知られてきてはいたが、まさか大阪で中国語圏の作品が翻訳上演されようとは思わなかった。私がプロデュースした1996、97年の高行健『逃亡』(龍の会)以来ではなかろうか。観にいかないわけにはいかないではないか。
幸いなことに、公演も成功だった。6月13日夜に観たこの『霊戯』は、力に満ちあふれていた。大阪での上演のこととてわずか三ステージなのだが、私が観た日は満員であったのも、喜ばしいことだった。誕生公演といっても、トリプルエム所属俳優は演出を兼ねた重藤大だけの、事実上のプロデュース公演らしい。
予想していたが、トリプルエムの上演台本は中国語からの翻訳ではなく、桐谷夏子訳の英語からのものだった。彼女が監訳の郭宝昆戯曲集『花降る日へ』(れんが書房新社)に収録されている。プログラムには、なぜ『霊戯』を上演しようと考えたのか、その理由は書かれていない。アジアの作品だから、というような特別の意識もなく、純粋にこの戯曲を読んで面白いと思ったから上演したのか。
『霊戯』の内容は、将軍、母、兵士、女、詩人という五人の亡霊が語る彼らの過去である。将軍たちは、半世紀も前に東方からこの島を占領しに軍隊とともにやってきた。母は、ある兵士と結婚し、新婚の翌日に夫は出征し、彼女は次の年に子を産んだ。まもなく彼女のもとに届いたのは死亡通知だった。彼女は「模範戦争未亡人」の称号を貰うが、まもなく子も死に、彼女は夫の遺骨をさがしにこの島にやってきて、軍に撃たれた。兵士は、忠実に上官の命令を実行し、敵や民間人を殺し、島を占領し、そして戦死した。女は看護婦として従軍し、戦いの前に兵士たちにレイプされる。告発しようとした彼女に、上官は言う。「兵隊たちの多くは結婚もしていない、女性に触れたこともない、女性との喜びも知らない。・・奴らの悲劇に比べ、あなた方の経験したことはたいしたことではない苦難だとは思わないか?事実、あなた方は知らないだろうが、戦争の局面での必要性に従って、兵隊達の必要を心から理解した何千人もの同胞姉妹がいるのだ。」彼女は告発を取り下げ、今度は慰安婦にさせられていく。詩人は従軍記者として、戦意昂揚のための偽りの報道記事と詩を書く。そして、今度は敵の反攻が始まった時、将軍は敵から司令部を防衛するため橋の爆破を命じ、六万以上の兵を見殺しにする。そして、彼らも死に、その魂は未だ家に帰れずこの島でさ迷っている。
この劇が描いているのが日本軍のシンガポール占領であるのは、多少の歴史知識があればすぐわかることである。しかし、この劇は単純に日本のアジア侵略を描いているのではない。中国人あるいは中国系アジア人が日本の侵略を描く時、日本は加害者として描かれるのが普通である。この『霊戯』はそうではない。登場人物は、加害者であると同時に被害者としても描かれ、それによって戦争の残虐さ、悲惨さがより浮き彫りにされる。「勤勉な、親切で、愛すべき人々が突然牛や狼の群れのようになる」悲劇である。もう一つ、この劇には日本に関する固有名詞はいっさい出てこない。天皇も、「偉大な指導者」と呼ばれるだけである。郭宝昆はあえて日本の名を出さないことによって、戦争をより普遍的に描こうとしたのであろう。日本人の観客としても、声高な日本糾弾がないために、より素直に劇の世界に接することができるのである。香港で上演された時、日本人に寛大すぎる、という反応が出たのを記憶している。
今回の上演はどうか。香港では中国・北京人民芸術劇院の一級俳優である林連昆らが出演しており、演技面での比較は不可能であろうが、トリプルエムの俳優たちも、その気迫を通して反戦の意志を観客に伝えることに成功している。将軍を演じた山田薫の存在感が記憶に残る。シンプルな舞台装置も、劇の世界の表現に貢献している。
ただし、『霊戯』の持つ日本との複雑な関わりまで表現できたかは疑問が残った。プログラムには、『霊戯』についての具体的な説明は何もない。若い観客たちは、この劇が描いているのは日本だということを理解できただろうか。劇の最後に、裕仁の写真や日の丸を出してもよかったのではないか。トリプルエムが今後どのような劇を上演していく意向か知らないが、郭宝昆などアジア演劇の上演はこれぎりにしないでほしい。
(せと・ひろし 演劇評論家・中国演劇研究家)
さまざまな“しんじょう”ー南船北馬一団『しんじょう』
市川 明
世界のどこかある国の日本人専用避難所が舞台。時間は20XX年で、日本が消滅したという前提になっている。避難所が閉鎖される直前の十日間、そこに隔離された五人の若者の「室内の闘い」である。時節柄、北朝鮮やイラクをどうしても想像してしまう。性格も生き方も違う五人の「心情」がぶつかり合い、重ねあわされ、いつしか一つの「信条」へと束ねられてゆく。舞台上の砂時計が天秤のように静かに下りて、砂が流れ落ちると、若者の中に変化が現れる。もう遅すぎたかもしれない。だが最後は「新庄」のようにピョンピョン跳ねて、こぶしを突き上げ、行動宣言をするのである。
新聞は蜷川幸雄演出『オイディプス王』のギリシアでの成功を伝えている。思えば現代の若者はオイディプスとは全く逆の状況にあるのかもしれない。オイディプスは社会のことをすべて見通していた。彼はスフィンクスの災いからテーバイの人たちを救うが、ただ一つ自分のことは知らなかった。自分の父親や母親が誰だとか…これに対して現代の若者は、自分や自分の家族、友だちについてはすべて知っているが、社会のことには無知・無関心である。彼らのファイルには個人情報はあっても、社会の動向に関するものはなく、核の傘の下に入って地球全体が破滅しても、そのときまで何も気づかない。そんな状況を棚瀬美幸は現在の世界と絡ませながらみごとに描き出している。
舞台中央、正方形の空間(部屋)に、ブランコの台座のような席がひし形に4つ置かれている。部屋の四隅には木箱の椅子がある。上には天秤のように吊り下げられたランプが二つ。(舞台美術:柴田隆弘)5人の若者が現れ、舞台上を回って席に着く。四人の男性と一人の女性。男性のうち岡山(末廣一光)がはみ出て、隅の木箱に座る。他の四人は「せんだみつお・コマネチ」ゲームに興じ、岡山は雑誌を黙々と読んでいる。単調なゲームが延々と続く。
半年の共同生活で、彼らにはヒエラルキーが形成されている。強者の鵜飼(橋本浩明)は岡山をのろまとののしり、雑誌を取り上げる。「動物園の猿」のようにじろじろ見られるのがいやで外出しようとしない。強い円の時代を懐かしみ、お金を振りかざせば何とかなると幻想する鵜飼に、日本人の「心情」の一つの典型を見る。強さと傲慢さの中に垣間見られる孤独、橋本はぶっちぎるようなせりふに「心情」の波紋を広げる。
この芝居で一番の存在感を示したのは榎本を演じた上田泰三だろう。「…してたん」「…やんか」「…せえへん」など独特の関西弁の柔らかなアクセントで弱者(岡山)を思いやり、人と人との「心情」に架橋する姿を鮮烈に示している。他の人たちがアメリカやヨーロッパへの脱出を考えているときに、インドネシア人のような風貌をした(失礼!)上田が「一番可能性があるのは、ここに永住することなんよ」とやんわり言うと、なぜか妙に説得力を帯びてくるのだ。
皆が脱落しても、一人でゲームを続ける鵜飼、「ウィー・アー・ザ・ワールド」を音痴なのに口ずさむ岡山、約束を破って一人で出て行った恋人明日香を思いやる池野(菅本城支)、一人では行動できず誰かにすがって脱出しようとする幸恵(谷弘恵)……惜しまれるのはたった一人の女性である幸恵を作・演出の棚瀬が描ききれていないことだ。男女の「心情」の交錯・ぶつかり合いなどによってその存在を際立たせることができたなら、芝居はもっとインパクトの強いものになっただろう。
世話係(監視役)のメルーさんが姿を消し、5人には餓死の危険性さえある。石が投げられたり、大量の手紙が放り込まれたりする。日本という国が消滅したことは間違いなく、皆それぞれの将来についていやでも考えざるを得ない状況にある。砂時計の砂が落ち、時はめぐり、最後に「信条」告白が始まる。幸恵は「宗教のない国、季節のある国、日本に似た国」に行きたいという。鵜飼は「何も考えないで生きてきた」自分を嫌悪し、「俺らが何もしなかったから、日本はなくなったんだ」と叫ぶ。池野は「しょうもないゲーム」をするより、失敗してもいいから「日本を作るゲーム」をしようという。日本ヘナチョコ青年党が宣言され、五人の決起集会がゲーム仕立てで始まるところで終わる。
メルーさんや現地の人たちが実際に舞台に登場するかどうかは別として、5人がコミュニケーションをとるために格闘する様が描かれてもよかったのではないか。外に向かっておかしな言葉で語りかけたり、見よう見まねの文字で手紙を書いたり…面白おかしい異文化コミュニケーションの劇ができたはずだ。静かで閉塞的な芝居なので、最後の「信条」告白が唐突でとってつけたように思えてしまう。「自分たちの無関心が日本を滅ぼした」というサビにいたる仕掛け、きっかけとなるような事件がやはり必要だ。イラク戦争と自衛隊の派遣という緊迫した状況の中で、野田秀樹の『オイル』とは違った、突き刺すような衝撃がこの芝居から走った。
(いちかわ・あきら/大阪外国語大学教授・ドイツ演劇)
*会場は劇場ロビーのすぐ下が墓地という、お寺の中の空間。住職の秋田光彦さんが公演をサポートしている。一心寺シアター倶楽部など新しい「タニマチ」の出現は心強い。
「南船北馬一団」は後に「南船北馬」に改名。https://nannsenn.jimdosite.com/
We Are The World 1985年、著名なアーティストが「USAフォー・アフリカ」として集結して、アフリカの飢餓と貧困を解消する目的で作られたキャンペーン・ソング。作詞・作曲はマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチー、プロデュースはクインシー・ジョーンズ。
ぼうぜんりせっと
垣尾優(かきおまさる)+藤村司朗(ふじむらしろう)。垣尾優は、95〜98年、冬樹ダンスヴィジョンにてモダン、コンテンポラリーダンスを習い、99〜00年、上海太郎舞踏公司に参加。藤村司朗とエンターテインメント・ダンス集団として呆然リセットを結成。観た人が衝撃を受け、破壊され、新鮮な一歩をふみだす力と生きる喜びが生まれる、そんなパフォーマンスをめざす。
人を「そんな気分」にさせるために~呆然リセット
上念省三
呆然リセットの「ブルースウィルス」という作品は、垣尾優の「始めます」という言葉でスタートしたり、藤村司朗がポケットからくしゃくしゃとメモを取り出して、そこに書かれた二人の出会いのいきさつを訥々と読んだりと、言葉による導入が観客の笑いを誘い、またそれによって観客をすばやく自分たちの世界に引き込むことに成功したものだった。
動きを言葉で解説する(ように見える)というダンス作品は、近いところでは既に山下残という前例がある。山下は2002年に「そこに書いてある」という作品を発表した。観客には分厚い本が配られ、ナレーターの朗読に合わせてダンサーが動く。「トンネル」と言えば股のぞきみたいな格好をするというふうに。また、2003年には「ダンスを語るダンス」と銘打って「透明人間」を発表(共にアイホール)。これらの作品を観てぼくが感じたのは、まず動きが言葉をなぞるのを観ることの不思議さであったが、それは言葉によって示されるものと動きによって示されるものとの質感の違いと、その違いを味わうことで「ゆらぎ」のように体感されるいくつかの感覚の間の時差のような差異そのものの面白さ、そしてその差異を感じている自分に対する興味、といったように、どんどん感覚がメタに流れて(本当は「深まって」と言うべきなのかもしれないが、深刻さとはちょっと味わいが違う)いくことの面白さだったと思う。「そこに書いてある」「透明人間」の二作によって、山下が作品の中で言葉を扱う手つきが、確かなものとなっている。
それに対して呆然リセットは、言葉を使うことにあまり自信がなさそうに見える。一見すると、作品にとって言葉はとりあえずの補完的メディアであって「本当は使わずに済むならと思ってるんですよね」と言い訳しながら、おずおずと言葉を発しているような印象さえ受ける。それは垣尾と藤村の訥々とした味わいのある語り口からもたらされると同時に、そこで語られる事柄が、男友だち二人の出会い……寒い下宿のこたつで雑魚寝をして風邪をひいたというエピソードであったりするように、半ばノスタルジックで半ば冴えない個的で「小さな物語」であることによる。ここで彼らは、世界がどうこうとか芸術表現としていかがかとか、そういうことは問わずに、ただ自分たちの独り言のような私的で小さな世界にとどまっているように見えるから、ぼくたちはのんびりと、笑いながら観ていられるように思ってしまう。
呆然リセットが面白いのは、そのようなフラットで日常的な感性を保ちながら、それらを突き抜ける時空を創り出すことができるところだ。身体芸術やら実験性などというような七面倒くさいことを考えさせる前に、観客を「楽しい」状態に引き込み、そしていつの間にか「すばらしい」と思えるような状態に誘い込んでいる。
さて、ではその呆然リセットのすばらしさとは何か。それは、ぎりぎりのカッコ悪さと懐しさだ。「ぎりぎり」というのには二つの意味がある。「ブルースウィルス」で言えば、さえない下宿で風邪を引いてしまったという話など、実にカッコ悪いのだが、そこからホールの壁にブルースの写真を何枚もペタペタと貼り、二人が「ブルーースッ!」「ウィルスーッ!」と声を限りに叫ぶのは、ぎりぎりのところで何かを通り越したような凄まじさがあって、背筋にかなり強い感動が走ったものだった。
そして彼らのダンスの動き自体にも、かなり微妙なぎりぎりのラインがある。シャープとか滑らかとかすごく速いとか、そういうエクセレントな形容には遠く、むしろ不器用でゴツゴツしたとかザラザラしたといった感触のある動きなのだが、そんな引っ掛かりが彼らのダンスの動きを深い魅力のあるものにしている。二人のコンタクトがいつもぼくに思い出させるのは、高校生だった頃、昼休みに教室の後ろや廊下で、プロレスの技をかけあったり、相撲をとったりしていた光景だ。ぼくたちのそんな不器用なぶつかり合いの中には、今ではもう再び得ることのできない掛け値なしの無垢なつきあいというものがあって、呆然リセットを観ることでそれを痛いように思い出す自分を発見する。それは彼らが言葉やしぐさを使って仕掛けた罠のような設定による部分もあるのだが、この痛さの大半は、彼らの動きの不器用なざらつきから来るものだ。もし彼らが同じ設定でエクセレントな動きを連発したら、その時そのエクセレントさによって、彼らとぼくの回路は絶たれ、彼らは舞台の上で奥のほうにどんどん遠ざかる存在となっていくだろう。垣尾によると、彼らは計算ずくでその不器用な状態を選び取っているそうだが、フフッ、それはどうでもかまわない。彼らが人をある状態にさせるためのぎりぎりで絶妙な間(ま)をもっていることを、同じ時代に存在する者として喜んでいるのだ。
(7月3・4日、於・ロクソドンタ・ブラック)
【時評・発言】
諫早発大阪行(博多乗換)
星野明彦
大阪から長崎県諫早市に転勤して、一年三箇月になる。転勤が決まった時周囲から「九州は演劇が盛んですよ」と言われたが、その言葉はある程度は当たっていた。
九州全体では18の市民劇場があり、東京の老舗劇団が約五万の会員を相手に、二箇月近い巡演を行っている。僕の所属する大村諫早市民劇場だけで、約1300名の会員がいる。これだけで大阪労演の会員数に匹敵する。ちなみに大阪市の人口250万に対し、大村・諫早両市の人口を合わせても18万である。
九州の中心である福岡市には公設民営の博多座があり、歌舞伎や「放浪記」等興行会社の枠を問わない、多彩な商業演劇が上演される。北九州市には昨年出来たばかりの、大中小3劇場を持つ演劇専用の北九州芸術劇場があり、蜷川幸雄や宮本亜門の演出作品等が招かれている。
そして地元劇団だが、北九州市には泊篤志代表の「飛ぶ劇場」、旧東独出身のペーター・ゲスナー率いる「うずめ劇場」という、全国的に名が知られ始めた二劇団がある。福岡市には100を超える劇団があり、中でも大塚ムネト主宰の「ギンギラ太陽’S」は、一公演につき三千人の観客を動員している。残念ながら福岡県以外の目立った劇団の噂は聞かない。しかし福岡・北九州まで足を延ばせば、来演・地元を問わず多彩な舞台に出会うことは可能なのだ。
しかし九州の演劇環境は、果たして本当に豊かなのだろうか。一年と少し表面を見ただけでも、様々な疑問が湧いて来た。
まず関西よりずっと盛んに見える市民劇場だが、老舗中心・中高年女性への偏り・他の演劇に対する会員の無関心、これらの問題点は関西と変わらない。しかし例会が行われる各都市のホールの多くは、関西よりさらに大規模になる(諫早文化会館は約13OO名)。そして活動は「前例会クリア」が第一目標となり、上演後の批評活動は行われない。「自分達が呼んだ以上舞台についてとやかく言わない」という方針があるという。
会員数が減る一方の近畿に比べれば、以上の方針が成功を収めているのだろう。しかし満員の客席のマナーはよいとは言えず、機関誌の感想文も舞台自体よりも会員拡大について書いたようなものが目立つ。平田オリザが「芸術立国論」で指摘した演劇鑑賞会の問題点・「東京での演劇を水増し」「会員数を文字通り水増し」を思い出さずにはいられない。「九演連」は、果たしてどれだけの主体的な観客を生んだのだろうか。
そして地元劇団の現状だが、九州唯一の演劇批評誌である「NTR」(柴山麻妃氏の編集・発行、現在まで13号)が大変参考になる。何号か読んで意外にも、「福岡からは関西は恵まれて見える」と感じた。
「NTR」10号(特集は「福岡のこれからの演劇」)の座談会で、柴山氏は福岡の製作者達に「全国レベルの舞台と言うのは福岡の都市圏では作られていない」という声がある、と問いかけている。その後「全国レベル」とは評価か人気か、という話になるが、別の号で劇評執筆者の一人は、「名古屋や京都にあるような全国レベルの」劇団が福岡にはないと書いている。この場合は「評価」だろう。
10号の別の座談会で大塚ムネトは大阪について言う。「メディアの現場があるんですよね(中略)役者としての求められる現場があるってことで。それに大阪の劇団は、ある程度になると東京公演もしますから、頑張れば東京でも役者として評価される」だから福岡よりも恵まれている、という訳だが、よく読めば関西を通して東京を観ているとわかる。
泊・大塚の両氏は一旦東京に出て福岡に戻り、福岡で芝居を作り続けている。東京や関西の公演も行う飛ぶ劇場は3回観たが、確かに「全国レベル」の「評価」に値する。一方のギンギラ太陽’Sは「福岡でしか観れない、受けない作品」と開き直り、かぶり物で福岡のビルや交通機関を擬人化する。今年一月に初めて観たが、その独特の気概は評価すべきとしても、かぶり物に役者が埋没していることに大きな疑問を感じた。
東京よりも距離が近いことから、九州と関西の演劇界は交流を始めたようだ。昨年の北九州芸術劇場第1回プロデュース「大砲の家」は泊篤志作・内藤裕敬演出で、東京・関西・九州の俳優が集まった。今年3月に長崎市の市民ミュージカルを構成・演出した岩崎正裕は、12月にやはり北九州芸術劇場プロデュースで泊の「冒険王」を演出する。「全国レベル」と言われながらも活躍の場に恵まれている訳ではない関西の演劇人が、発展途上とされる九州の演劇界に対して何が出来るのか。そして「全国レベル」の現代演劇が本当に生まれるのか。九州の中心から少し離れた諫早から見つめていきたい。
(ほしの・あきひこ/会社員)
大村諫早市民劇場 年に6本のプロの劇を諫早文化会館で観劇する団体。(2025年調べ)
New Theater Review
柴山氏は2023年ブログ「福岡演劇情報」を開設。https://newtheatrereview.com/
「大砲の家」に関する地域創造の記事 https://www.jafra.or.jp/library/letter/backnumber/2003/104/4/1.html
大阪春の演劇まつりhttps://haruen2.wixsite.com/haruen
大阪府立青少年会館
大阪市中央区森ノ宮中央2-13-33にあった大阪府営の多目的ホール。1960年竣工。小ホールに当たるプラネットホール、は若手アマチュア劇団にとって貴重な存在であったが、橋下徹大阪府知事が掲げる「大阪維新プログラム」の一環で2009年6月30日で廃止された。跡地は「ファインシティ大阪城公園」という15階建てマンション。
-大阪の劇の営みの中での-ある演劇祭のこと
粟田倘右
この大阪に《春演》と呼ばれて、もう28年も続いている演劇祭があります。正確には『大阪春の演劇まつり』と言います。秋には『大阪新劇団協議会』に加盟する劇団による『大阪新劇フェスティバル』が持たれ、大阪の《新劇(現代演劇)》の存在を示しています。その秋に対しての「春」というわけではないのでしょうが、今年も滋賀、名張からの劇団も参加し、18劇団が4月から、森の宮の府立青少年会館の『プラネットホール』を主会場に、各々の思いの丈を込めた舞台を競い、これまでに15劇団が公演を終えています。そして、あと3劇団の舞台が7月末まで続きます。(この冊子が出た頃には全部終わっている筈です。)
この演劇まつりを立ちあげ、主催しているのは《大阪自立演劇連絡会議》《財団法人大阪府青少年活動財団(ユースサービス大阪)》、そして今では殆ど大阪では実際的な活動は中止しているようですが、《日本アマチュア演劇連盟近畿支部》の三団体で、毎年の参加劇団からの『実行委員会』が具体的なプログラムを進めていっている様です。
この《春演》には、秋のフェスティバルのメンバーでもある『劇団未来』『劇団息吹』『劇団往来』そして、今年は上演参加できなかった『劇団大阪』など、大阪の演劇を何十年にも亘って担ってきた劇団も参加しています。これらの劇団を中心軸に、その参加劇団の大半は、所謂、<若い劇団>です。毎年、何劇団かが入れ替わり立ち替わり、新しい劇団の名前が並びます。「もうヤメテくれよ・・」と言いたくなる程の舞台をお披露目してくれる劇団もときにはあります。そういう劇団も認めての《春の演劇まつり》です。《職業(的)劇団》又は《専門集団》による演劇祭ではない、ということです。そうです、《市民演劇》による『演劇まつり』です。かつて、何十年か以前、《自立演劇(劇団)》や《サークル演劇(劇団)》或いは《地域演劇》(《アマチュア演劇》)とも呼称されていた劇団による『演劇祭』といっていいでしょう。
著名な役者が居る劇団でもない。朝晩のお茶の間のTVに見られる顔も見あたらない。そんな芸能ニュースは勿論、新聞等の芸能欄を飾り、賑わすには余りにも地味な劇への行動には違いありません。大方の人々を引きつけるには、ニュースバリューが低い、弱いのでしょう。そして事実、新聞、TVなどのマスメディアが、この『春演』を芸能欄や文化欄で報じることも殆ど無いようです。(私が朝夕、目を通しているA紙には、これまで全くと言っていい程にありません。)ですが、《春演》に参加して来ない、それこそ何百もの劇団の殆どが職業、プロとして成立できない大阪の現実の中で、《大阪の演劇》を語る上では、大切なプログラムの一つには違いないと思うのです。
持ち出しばかりの、儲かるなんて考えられない劇へのエネルギー。身銭を切っての行為です。自分に対して納得しなくては成立しない《劇への営み》です。舞台を駆けまわる若さだけの役者を観ていて、その劇の内容の良し悪しはともかく、屈託のなさに、演劇って、つくづく「魔物」だなァ、と思わずには居られません。そんな『春演』ですが、毎年、参加劇団の半数以上の劇団内創作が並びます。今年も12劇団がオリジナル作品で驚きますが、気になることが二つあります。
ひとつは、劇のしつらいが、仮想の世界であっても、その劇の当事者と劇の世界の『距離』の近さです。それは生きることの世界の小ささ、想像力の無さ、夢の無さではないのかと思ってしまいます。もうひとつは、そのオリジナル作品、戯曲が一回だけの上演で、その殆どが終わってしまうことです。まるで蝉の命のように-。何か悲しい、もったいない-。
そうした中で、作家集団でもある『りゃんめんにゅうろん』の『月見荘秘話』が、古アパートの各室の人たちの同じ時間にかいま見えた姿を描きながら、そのアパートの50年の時間を浮かび上がらせた、3人の作者によるオムニバス仕立ての舞台。そして、既成作品の舞台でしたが、細部に亘る実に綿密な解釈による演出で、或るサラリーマン一家のゆれ動く一日を描き出した『劇団未来』の舞台(ふたくち・つよし作『山茶花さいた』)が印象に残りましたが、来年の29回目の『春の演劇まつり』では、どんな舞台に出会えるのでしょうか。楽しみです。そして、『春演』こそが、《『生まれた土地』の演劇》という、かつて加藤衛さんが大切にしておられた言葉を立ち上がらせる舞台ではないか、と改めて思うのですが……。
(あわた・しょうすけ/演出者・演劇評論者)
演劇の教育と俳優の養成 (2)
菊川 徳之助
日本には「演劇大学」がない。驚きである。美術大学も音楽大学もあるのに、である。俳優やスタッフや演劇研究者を育成するという考え方が日本にないことが証明されていると言えるだろう。日本の大学は、<学部・学科・専攻・コース>といった設置の仕方になっている。「演劇大学」がなくとも「演劇学部」を設置している大学くらいはあると思う。ところが、日本の大学には「演劇学部」もないのである。<学部>として存在していないのである。わずかに「芸術学部」の中に「演劇学科」を設置している大学が三校あるにすぎない。つまり、<学科>の段階に来てやっと演劇が顔を出すというわけである。その他は、例えば、「文学部」(文芸学部・人文学部など)の中に「演劇専攻」を設置しているといったものが多い。文学部の中にあるということは、演劇の専門性が百%保障されていないことを物語っている。また、「演劇学科」という名称も昨今では、<パフォーミング・アーツ学科>といったような<演劇>という文字をともなわないものが目につく。
現在、日本の大学は700校もあるが、<実技>を伴った演劇コースを設置している大学は、関東地方に四校、関西地方に三校、九州に一校あるのみである。このほかには、短大が東京に一校、九州地方に一校ある。そして、学問(理論)面を中心にして演劇学を学ぶ演劇コースを設置している大学が、関東地方に三校、関西地方に一校、あるのみである。しかし、これらの大学は、ほとんどが私学であって、関西地方の一校を除いては、国立や公立の大学はないのである。国が演劇に全く無関心だと言っていい状態を示している。明治という新しい時代に、<演劇改良>もまた重要な課題として省みられた時があった。そして、この時に演劇が何らかの形で、日本人にとって大切な文化としての位置、演劇の位置を獲得できていれば、さらにはまた、教育の中にも演劇を設けることに成功していたなら、現代の日本は、経済面のみの成功ではなくーー今は経済破綻へ向かってまっしぐらかもしれないがーー文化面においても成熟した文化国家を形成していた可能性は大いにあったと思われる。明治期の失敗は現代まで尾を引いていると言えば、言い過ぎか。
芸術大学であるところの東京芸術大学や京都市立芸術大学に「演劇学部」があって当然な気もするが、そして、時には、「演劇学科」を設置する計画が浮上したこともあったようであるが、現実は、これらの大学に、演劇の科目が一つでも設置されていれば良い方という程度が現状である。昭和23年片山内閣の時、文化構想として<演劇>も入った芸術大学が構想されたようである。「現在の音楽、美術両校を統合、これに映画演劇教員養成部を加えた5学部として芸術大学をつくろうとするもの」(大笹氏の『日本現代演劇史』の東京新聞の記事より)、とある。片山内閣が総辞職しなかったら、現在の音楽、美術の東京芸術大学と違ったものが出来ていたかもしれない。残念である。
少子化で、授業料の高い演劇学科に進学希望する学生は、経済学部や法学部には程遠いが、それでも、将来の俳優や演劇人を夢みて受験する学生は毎年いる。作家の五木寛之氏がいつぞや新聞紙上に、金沢に演劇大学をつくりたい、と言った記事が出たことがあった。金沢には確か美術大学があり、芸術の匂いのする街である。しかし残念ながら、今日まで金沢に演劇大学が出来たとは聞いていない。ある時期、演劇実践教育として画期的な大学が出来た時があった。それは、劇団俳優座付属の俳優養成所が、短大ではあるが、2年制で、さらに専攻科2年で、大学並みの4年間となる学校に移行された時である。現場の演出家や劇作家、俳優などが、大学で演劇を教えるのであるから、演劇教育そのものが少ない日本の現状には、紛れもなく画期的なことであった。そしてなによりも、この大学は、卒業生の中から劇団俳優座へ入団出来るという大きなメリット、特徴を持っていた。演劇専攻を持つ他大学からは、この短大の演劇専攻は、ただならぬ存在なのであった。何故ならば、他大学の演劇専攻生は、大学の演劇学科を卒業しても劇団に入れる保障は何もなかったからである。いや、それどころか、卒業生から見れば信じられないことであるが、四年間の演劇教育を終えても、劇団に入るためには、その劇団の付属の養成所へもう一度試験を受けて入らなければならないのである。そして、もう1年なり2年なり、大学の演劇学科で学んだと同じような基礎訓練や演技訓練を受けなければならないのだ。しかも、大学の四年間授業料を支払って来たのに、また再び劇団の養成所へ授業料を支払わねばならないのである。日本の現状は、演劇専攻を持つ大学の卒業資格と劇団の俳優になれることとは、直結していないということなのである。この現状は、演劇人養成の環境としては、実によくない状態である。不幸である。勿論そこには、国家が何もしない状況では、劇団の自分たちで養成所を造らざるを得なかったという劇団の事情があり、大学の演劇教育に信頼を置く環境になかったことも考えねばならないだろう。そしてまた、俳優座が再び劇団自身の養成所を復活するという状況も現れた。大学の演劇教育に問題ありと、これは考えねばならない事態なのか。大学の演劇教育は、どのような問題を抱えているのか、その検証も必要であろう。大学の演劇教育の現況、問題点をもう少し考えてみたい。
(きくかわ・とくのすけ/近畿大学演劇専攻教授)

書影は2007年刊ペーパーバック版
杉山太郎著『中国の芝居の見方』に寄せて
藤野真子
本書は3年前に交通事故で急逝した杉山太郎氏の遺著である。思えば、杉山氏と会うのは、いつも中国であった。初対面は1995年の正月、本書でも触れられている「梅蘭芳・周信芳生誕100周年京劇公演」(第二章で言及)の上海公演の場であったが、当時の私は博士課程の院生で、演劇研究を志しつつも実地の観劇経験に乏しく、実に語り甲斐のない相手だったことだろう。しかし同年、上海での留学生活を始めた私にご馳走して下さったばかりか、ご自身が興味を持たれた書籍(第五章・書評で取り上げている樋泉克夫著『京劇と中国人』)を贈って下さるなど、のちのちまで何かと心にかけて頂いた。本書では一カ所、「上海の演劇の専門家」という実態を慮ると汗顔ものの名称で私の名が一瞬登場するが、生前、「上海京劇に着目するとは面白いセンスの持ち主だ」と評されて(?)いた旨聞いた。氏から真意を伺うことはできなかったが、あらためて本書の、上海京劇院『狸猫換太子』三本を日本で通し公演するなら25,000円でも安い!というくだり(第二章「第二回京劇芸術祭を見て」)などを読むと、それも少しはわかるような気がする。
前置きが長くなってしまったが、肝心の本書の構成をまず紹介すると、第一章「戯曲を見るということ」、第二章「中国演劇時評Ⅰ」、第三章「中国演劇時評Ⅱ」、第四章「中国演劇論」、第五章「書評」、附章「日本語教育・人口論」の六つの部分に編集されている。実質的には、越劇を中心に杉山氏の中国演劇観がいかんなく披瀝されている第一・第四章、そしてこれもこまめに現地に足をはこんだ氏にしか書き得ない第二・第三章の劇評・観劇レポートの二部構成といってもよい。特に後者はボリュームに富み、伝統劇・話劇と劇種を問わず多くの舞台について書きとめた極めて魅力的な文章群であるが、これについては他に相応しい発言者があろうと思うので多言はしない。少し記しておくと、氏は個々の劇種や演目、俳優、演出家に関する豊富なデータを脳裏にストックしておられたが、芝居の善し悪しに関してもその蓄積に基づき、決して安易に妄断していないことが、これらの文章、特に贔屓にしていた劇団や俳優への冷静な批評から見て取れる。一方、「初対面」の舞台については、努めてフェアなまなざしを保とうとすると同時に、何らかの旨味にたどり着くまでしゃぶりつくしてやろうという貪欲な姿勢も強く感じられる。表面だけを撫でて「こんなものはダメだ」と切り捨てることはしないのである。
杉山氏は中国演劇に対峙するスタンスを潔すぎるほど明瞭に示した人物である。「中国の伝統演劇では、昨日と変わらない今日の舞台には価値がないと、かつて来日した中国京劇院の俳優から聞かされ、その新しい試みにこそ価値を認めようとするのが、筆者の立場である」(本書6頁)という宣言からも、その一端がうかがえる。そして、この直後に述べられる「だからといってそれは、何が何でも新しければよいということではない。あくまで伝統に立脚してということが条件になるのは当然であり、それはそもそも『伝統』ということ自体を重視しない越劇を見る場合でも同じことである」という言を皮切りに語られる冒頭第一章の越劇論(『火鍋子』連載「戯曲を見るということ」)こそ、本書の圧巻であると言える。実際、その商業性やきらびやかなイメージばかりにとらわれて、越劇をまともな研究対象として見ようとしない人々が、アカデミズムの「ギョウカイ」には結構多い。しかし、杉山氏の叙述と重なる部分もあるが、私が見るに、発展時期および場所の特殊性、上演形態の変遷、演目の傾向と思想性、他メディアとの連携性、何よりも残存資料の質・量からして、これほど多様な論を展開しやすい劇種は他に無い。
こと本章における杉山氏の論考で興味をひかれたのは、越劇の主流である女子越劇と、ある種異端的ポジションを占める男性役者の混じる越劇との差異を論じた部分である。「女性のための演劇」である越劇が求めた、「現実社会には存在しない女と共に闘う同志としての男」、つまり「舞台の上にしか存在しない女の夢の結晶」を演じうるのは女子小生のみであると杉山氏は断言する(11~12頁)。そしてこのように作り上げられた男性像に対する「女性観客から掛けられる思い」に、俳優の実際の性別により「本質的な差異」が生じることを一つの根拠として、趙志剛に代表される「現実の」男性が舞台に立つ越劇を別の劇種と見なしている点には、何かと考えさせられるものがあった。個人的にはここから、歴史も性質も観客の嗜好も越劇とは大きく異なるものの、民国期を境に男旦から女旦へ移行した京劇の場合、同様の変質を見出しうるのかということを考えてみたくなった。
他にも示唆に富む箇所は多数あるのだが、ここで紙幅も尽きたので、また別の機会に譲ることとしたい。
杉山太郎『中国の芝居の見方-中国演劇論集』(好文出版 2004年6月 3,800円)
(ふじの・なおこ/関西学院大学)
【編集後記】
『あくと』2号をお届けする。創刊号は編集に手間取り5月31日発行になったが、2号は8月上旬にお目見えする筈である。これが本来の発行時期で、以後、3号は11月上旬、4号は05年2月上旬発行というスケジュールになる。
創刊号は、いろいろ反省も多いが、ともかく世に出すことができた。驚いたのは、AICT日本センター公式サイト掲載の案内をみて、定期購読を申し込んでくださった方が何人もいたことである。これ以外にも、定期購読者は順調に拡大している。これほど編集の励みになることはない。とはいえ、安定した有料発行部数にはまだほど遠い。これからも定期購読者獲得に努めたい。
『あくと』は関西という地域に密着した演劇批評誌であるが、関西の問題しか取り扱わない雑誌にする気はない。関西から、全国、全世界に向けて問題提起できる雑誌にしていきたい。執筆者も、関西在住者を中心にはするが、それに限定するつもりもない。今号では九州在住の星野明彦氏に寄稿していただいたが、これからも、関西以外の地区の筆者による原稿も掲載していきたい。
とはいえ、『あくと』の一番の課題は、持続させることであろう。思い切った特集を組んだり、もっと分厚くしたり、発行回数を増やしたりしたい気持ちもあるが、この種の刊行物は続かなければ意味が半減するのである。『あくと』の現在の体裁も、まず長続きさせることを前提に作られている。そして、歩きながら考え続け、少しづつさらに良い雑誌にしていきたい。これからも、読者の皆さんのご支持をお願いしたい。 (瀬戸宏)